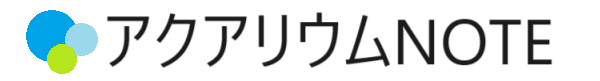小学3年生になると理科の授業でメダカの観察をする小学校も多いですが、夏休みの自由研究で「メダカの観察」をテーマにするのもおすすめです。
メダカを育てていない方も、水族館などでメダカ飼育をしていたり、科学館などで自由研究に向けたイベントを行っていることもあるので、そういったところで学ぶこともできます。
ここでは、実際に自由研究で使用した題材・メダカの写真をご紹介したいと思います。
自由研究の参考にしてみてくださいね。
自宅にメダカがいないときはどうしたらいい?
自宅でメダカを飼育していないと書けない、ということはなく、水族館や科学館などで自由研究向けのイベントや展示などでメダカの観察を行っていることがあるのでそういったところを利用して作成できます。
また、実物の写真でなくても図鑑などを参考に色鉛筆やサインペンなどでイラストを描くと、文章だけで書くよりより分かりやすい作品になります。
■自宅で飼育していない場合の作成方法
- 水族館・科学館などの施設を活用
- 図鑑・写真を見てイラストを描く
公共施設の展示物を写真に撮って使いたい場合は、施設の方に許可をもらってから行うようにしましょう。
また、書籍、図鑑などの写真を撮影し無断で使用すると著作権法違反となる場合があるので、許可されていないものに関しては撮影して使うことは避けましょう。
テーマ➀メダカの産卵

メダカは日照時間が13時間以上、水温が20℃以上になると産卵します。
産卵時期は6月~10月ごろが多いです。
室内でヒーターを入れて水温を20℃以上に安定させると、冬でも産卵することができます。
産卵するとお腹のあたりに5~10個ほどの透明な卵が上からも見ることができます。
テーマ➁メダカの卵の観察

メダカの卵を置く場所は、6月ごろなら室内より屋外の方が空気に触れやすいのでおすすめです。
7月以降は暑さで弱ってしまうこともあるので、室内で管理する方が良いでしょう。
直射日光の当たらない場所に置いて孵化するのを待ちます。
メダカの卵は透明で大きさは1~1.5mmほど。
メダカの卵を見つけると成長がとても楽しみになりますね。
こんな卵は要注意
透明でなく中に曇りがあったり、周りにフワフワとモヤがついている場合は卵が成長していない、カビが生えている卵なので、他の卵に影響を与えないように取り除きます。
スポイトなどを使って元気な卵から離しましょう。
カビの生えた卵と元気な卵がくっついていると、元気な卵もカビの影響を受けてしまうことがあります。早めに離しておくと影響をうけにくくなります。
テーマ③メダカの卵の孵化

産卵から7~8日目になると卵の中にメダカの目や体がよく見えるようになります。
ここまでくると孵化はもう間もなくです。
産卵から10日ほどするとメダカが孵化して5~7mmほどの稚魚(仔魚)が泳いでいるのを確認することができます。
孵化後のメダカのごはんは?
孵化から3日ほどはご飯を食べなくてもメダカが持っている栄養で育ちますが、3日以降は稚魚用のご飯を細かくすりつぶしてあげると少しずつ食べるようになります。
しっかり大きくなるために栄養補給はとても大切なので、1日に2回程度ご飯をあげるのが理想ですが、食べ残しが多い場合は量を少なくして様子を見ます。
エアーポンプは必要?
卵~稚魚を観察するときは自然風で容器内に十分に酸素を取り入れられるのでエアーポンプがなくても成長することができます。
エアーポンプを使うと水流の影響を受けて疲れやすくなり稚魚が弱ってしまうので、エアーポンプは成魚になって室内飼育をするタイミングで入れると良いでしょう。
テーマ④メダカの仔魚~成魚

体の大きさの違い、特徴をイラストや写真で説明していきます。
仔魚
生まれて間もないメダカの子ども。
稚魚
仔魚から成長すると背骨がはっきり見えてきて稚魚と呼ばれるようになります。
幼魚
お腹が少し膨らんできて全体的にメダカらしい形になってきたころを幼魚と呼びます。
若魚
見た目は成魚に近いですが、成魚に比べると体全体が細く一回り小さいです。
若魚は繁殖はまだできません。
成魚
全体的にふっくらと丸みを帯び、メダカらしい丸々としたしっかりした体つきになると成魚と呼ばれるようになります。
成魚になると繁殖できるようになります。

その他のテーマ➀メダカの卵を採卵してみよう
採卵の方法➀産卵床を使う方法
一番簡単な採卵方法は、産卵床を使う方法です。

このような産卵床を入れておくと、産卵したメダカが卵をこすりつけます。
卵を見つけたら観察用の飼育ケースに移して稚魚が孵化するのを待ちます。
次の➁では、メダカのお腹から直接採卵する方法をご紹介していますが、こちら↑のやり方の方が失敗しにくくメダカにもやさしいのでおすすめです。
採卵の方法➁絵筆で卵を取る方法
産卵しているメダカがいたら、小さいネットに誘導してきれいな絵筆でお腹をやさしくこすります。
卵が筆にくっつくので、水を入れた大きめのプラカップに移し、指でやさしくこすり落とします。
産卵から10日ほどすると稚魚が孵化します。

小さめのネットにめだかを優しく誘導し、お腹の卵に絵筆を軽く当てて左右に振ると卵が筆にからみつきます。
採れた卵はすぐに飼育水を入れた容器の中に入れて、風通しの良い場所で管理しましょう。
産卵から5日以上経つと卵がやわらかくなり、移すときにつぶれやすくなるので見つけたら早めに移動しましょう。
その他のテーマ➁メダカの飼育水の作り方を紹介しよう
飼育水は水道水を容器に入れて一晩置いておくだけでもカルキを抜くことができるので、一晩置いた水道水を飼育水として使うこともできます。
すぐに作りたい場合は市販のカルキ抜きを使うと、飼育水をすぐに作ることができるので、使っているカルキ抜きのアイテムを紹介するのもいいですね。

↑このようなメダカの飼育用のカルキ抜きもあります。

↑他にも飼育しているお魚がいる場合はこちらもおすすめです。
どちらも水道水に混ぜるだけなので簡単にお魚が快適に過ごせる飼育水を作れます。
自由研究作成の所要時間のめやす
初めて理科の自由研究をした場合で、下書き~模造紙に書き込むまで4日ほどかかりました。
慣れている方はもう少し早くできるかもしれません。
やっているうちにいろいろ書きたくなってきますが、まずは無理のない範囲で分かりやすい作品になることを目標に進めていくと良いですね。
おすすめの図鑑

DVDつきでメダカ・金魚・熱帯魚の解説やお世話の仕方など、分かりやすく説明してくれます。
メダカの基本的な生態、体のしくみ、育て方を子どもにも分かりやすく解説しています。
水替えの仕方、屋内・屋外での飼育方法、繁殖させる方法など初心者にもやさしく教えてくれるのでメダカ飼育のバイブルとしてもおすすめです。
メダカの他にも金魚や人気の熱帯魚「ベタ」の解説も収録されているので、おうちで飼育できるいろんなお魚について知ることができます。
図鑑の内容をそのまま書くと冒頭の写真・図と同じように著作権法違反となってしまうことがあるので、丸ごと写すのは避けましょう。内容を参考にした場合は、自由研究の最後に参考文献:○○図鑑といった形で記載しておくと良いです。
まとめ
夏休みの自由研究のテーマについて、今回は小学3年生ごろに向けた「メダカの卵の孵化から成魚になるまで」をご紹介しました。
おうちで飼育していなくても、公共施設のイベントや図鑑・書籍を使ってイラストで分かりやすく説明することもできるので、ぜひ参考にしてみると良いと思います。
慣れていない方はまず、無理のない範囲で、項目を増やしすぎないようにし、全体的に分かりやすい内容になるといいですね。
授業の予習にもなるのでメダカの産卵~成魚について夏休みに調べてみてくださいね。